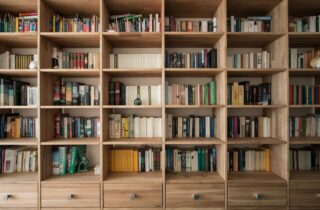お気に入りの曲ならまだしも、なぜか昔のCMソングや、特に好きでもない曲が、頭の中で音楽がずっと流れる…そんな経験はありませんか?
一度始まると、自分の意思とは関係なく延々とリピートされる、うっとうしい脳内ループ。この現象、「どうにかして頭から音楽が消えないものか」と悩んだことがある人も多いはずです。
その現象には「イヤーワーム」という名前があり、脳の仕組みに基づいた、はっきりとした原因と、科学的な対処法が存在するのです。
その現象の名は「イヤーワーム(耳の虫)」
この、頭の中で音楽がずっと流れる現象は、専門的には「イヤーワーム(Earworm)」と呼ばれています。直訳すると「耳の虫」。まさに、虫が耳の中にいるかのように、音楽がこびりついて離れないイメージから名付けられました。
研究によっては、人口の90%以上が週に一度は経験するとも言われており、決してあなただけに起きている特殊な現象ではありません。
なぜ起きる?脳のアイドリングと「認知的なかゆみ」
では、この厄介な脳内ループは、なぜ発生するのでしょうか。主な原因は2つあると考えられています。
1. 脳の「アイドリング」中に忍び寄る音楽
私たちの脳は、ぼーっとしたり、単純作業をしたりしている「アイドリング状態」の時、DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)という回路が活発になります。この脳のおしゃべりタイムに、記憶の中からふと音楽データが引き出され、再生が始まってしまうのがイヤーワームのきっかけです。
2. 曲が中途半端で「かゆい」脳
そして、一度始まるとループが止まらない最大の原因は「認知的なかゆみ」にあると言われています。
特に、曲のサビだけなど「一部分」だけが再生されると、私たちの脳はそれを「未完了なもの」として認識し、強いムズムズを感じます。そして、そのムズムズ(かゆみ)を解消しようと、脳は何度もその不完全なメロディを再生し、完成させようと試みるのです。これが、頭の音楽が消えない脳内ループの正体です。
(※この現象は、心理学における「ツァイガルニク効果」と深く関連しています)
【実践編】うっとうしい脳内ループを断ち切る、5つの科学的アプローチ
では、この無限ループを断ち切るにはどうすればいいのか。科学的に有効とされる5つの方法をご紹介します。
1. 曲を「最後まで」しっかり聴く
最もシンプルで効果的な方法です。中途半端で「かゆい」状態の脳に、曲の終わりまでをしっかり聴かせることで、「これで完了した」と満足させ、ループを終わらせる効果が期待できます。
2. ガムを噛む
一見、不思議な方法ですが、これは科学的な裏付けがあります。音楽、特に歌詞のある曲の脳内再生は、言葉を発する時と似た脳の領域を使います。ガムを噛むという全く別の運動で口を忙しくさせることで、脳の再生機能を物理的に妨害するのです。
3. 別の「言葉を使う作業」に没頭する
これも②と同じ理屈です。アナグラムやクロスワードパズルを解く、小説を読む、誰かとおしゃべりするなど、脳の言語野を別の作業で上書きしてしまいましょう。「頭の音楽が消えない」と感じたら、別の思考で脳を忙しくさせるのが効果的です。
4. 「解毒ソング」を用意しておく
どうしてもループが止まらない時のために、別の曲で上書きする方法です。国歌や校歌など、個人的な感情移入が少なく、かつメロディラインがはっきりした曲が「解毒ソング」として有効だと言われています。ただし、その曲が新たなイヤーワームになるリスクも…。
5. あえて「気にしない」
「止めよう、止めよう」と意識すればするほど、かえってその思考に執着してしまう「皮肉過程理論」という心理現象があります。イヤーワームも同じで、気にすればするほど消えません。「ああ、また始まったな」と客観的に受け流し、自然に消えるのを待つのも、一つの有効な手段です。
まとめ
頭の中で音楽がずっと流れる「イヤーワーム」は、うっとうしい反面、私たちの脳がいかに音楽と記憶を深く結びつけているか、という興味深い証拠でもあります。
その正体と対処法を知ることで、厄介な「耳の虫」も、少しは愛せるようになるかもしれませんね。