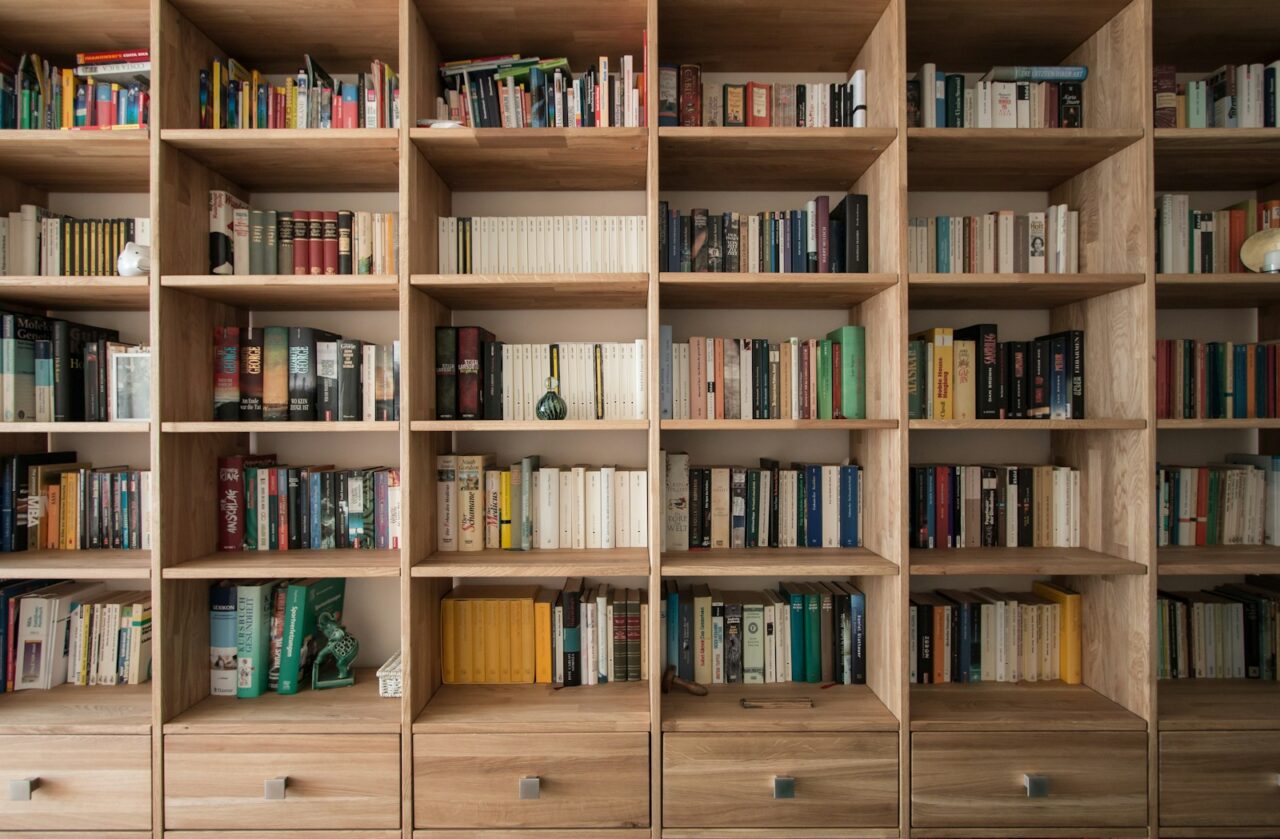
「時間にルーズなのは社会人として失格だぞ。お前のために言うけど、もっと5分前行動を心がけろよ」
いつもギリギリに出社してくる上司に、そう説教された経験はありませんか?
あるいは、子どもの好き嫌いを叱る親が、実はブロッコリーを避けていたり…。
言っていることは正しい。でも、「あなたもできてないじゃないか!」と喉まで出かかった言葉を、ぐっと飲み込む。そんな理不-尽な経験は、誰にでもあるはずです。
なぜ、人は自分のことを都合よく「棚に上げて」、他人を批判できてしまうのでしょうか。
それは、決してその人の性格が悪いから、というだけではありません。私たちの脳に組み込まれた、巧妙かつ強力な「自己防衛」のカラクリが働いていたのです。
【第1章】心理学の答え:「根本的な帰属の誤り」という心のクセ
この「棚上げ」現象を説明する、非常に有名な心理学の概念があります。それが「根本的な帰属の誤り(Fundamental Attribution Error)」です。
これは、物事の原因を考える(帰属させる)際に、私たちの心に生じる特定の「クセ」を指します。
- 他人の行動の原因を考える時 → その人の「性格」や「能力」など、内的な要因に求める。
- (例)同僚が遅刻した → 「彼が時間にルーズだからだ」
- 自分の行動の原因を考える時 → 「状況」や「環境」など、外的な要因に求める。
- (例)自分が遅刻した → 「電車が遅延したせいだ」
私たちは無意識のうちに、他人の失敗は「その人自身の問題」と断定し、自分の失敗は「仕方なかった」と正当化する、二重基準(ダブルスタンダード)で世界を見ているのです。棚上げ発言をする人は、この心のクセに無自覚なまま、あなたを「内的な要因」で裁いているのかもしれません。
【第2章】脳科学の答え:脳は自分を守るのに必死!「自己奉仕バイアス」という最強の盾
では、なぜそんな不公平な心のクセが生まれるのでしょうか。その鍵は、脳の最優先事項にあります。それは「自尊心(セルフエスティーム)を守り、自分という存在を肯定すること」です。
「自分はダメな人間だ」と感じることは、脳にとって多大なストレス。そこで脳は、自分に都合の良い解釈を自動的に行い、心を守ろうとします。この働きを「自己奉仕バイアス(Self-Serving Bias)」と呼びます。
- 物事が成功した時: 「自分の能力が高かったからだ」(自分の手柄にする)
- 物事が失敗した時: 「運が悪かった」「タイミングが最悪だった」(外的要因のせいにする)
これは、心を健康に保つための、いわば脳のセーフティネットです。自分のことを棚に上げて説教する人は、この自己奉仕バイアスが強力に働き、「自分は正しく、教える立場にある」という心地よい自己認識を必死に守っている状態、と見ることもできます。
【第3-章】処方箋:「棚上げ名人」への対処法と、自分がそうならないための自己客観視テクニック
この厄介な心のカラクリと、どう付き合っていけばいいのでしょうか。二つの視点から処方箋を提案します。
1. 「棚上げ名人」へのスマートな対処法
相手に「あなたもでしょ!」と真正面から反論するのは、相手の自己防衛本能をさらに刺激し、関係を悪化させるだけです。おすすめは、相手を客観的な視点にそっと誘導する質問法です。
- 相手: 「君は計画性がないから、いつも締切ギリギリになるんだ」
- あなた: 「ご指摘ありがとうございます。確かにそうかもしれません。ちなみに、もし予期せぬ緊急の仕事が3件も重なってしまった場合、〇〇さんなら、どのように計画を立て直すのが最も賢明だと思われますか?」
ポイントは、相手を主語にするのではなく、一般的な「状況」を仮定して質問すること。これにより、相手は自分の経験を棚から下ろし、客観的なアドバイザーとして状況判断をせざるを得なくなります。
2. 自分が「棚上げ名人」にならないための自己改革
恐ろしいことに、このバイアスは誰の脳にも存在します。自分も無意識にやってしまうのを防ぐには、自分の思考のクセを客観視(メタ認知)するトレーニングが有効です。
おすすめは、一日一行の「言い訳ログ」です。
一日の終わりに、その日自分が「〇〇のせいだ」と思ったことを、一つだけ書き出してみましょう。
「急に話しかけられたせいで、集中が途切れた」
「資料が分かりにくかったせいで、理解に時間がかかった」
これを続けると、自分がどのような状況で、何を「外的要因」のせいにしがちなのか、そのパターンが見えてきます。パターンに気づくだけで、無意識の棚上げは驚くほど減っていきます。
【まとめ】「棚上げ」は人間の本能。だからこそ知恵が必要
自分のことを棚に上げて他人を批判するのは、一見すると非常に意地悪な行為に見えます。しかしその裏には、自尊心を守ろうとする、人間的で、ある意味では健気な脳の働きが隠されています。
このカラクリを知ることは、理不尽な説教に心を乱されにくくなるだけでなく、「自分もやってしまうかもしれない」という謙虚さをもたらしてくれます。
人間の本能だから仕方ないと諦めるのではなく、その仕組みを知り、一歩引いて自分と他人を見つめること。その知恵こそが、ストレスの多い人間関係を、心穏やかに渡っていくための羅針盤となるはずです。











