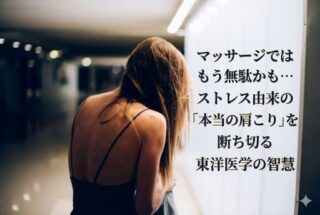「なんだか最近、元気が出ないな…」
「気力はあるのに、どうも風邪をひきやすい…」
「東洋医学の『気』って、一種類だけじゃないの?」
こんにちは!あなたの心と体の健康を応援する「とろLabo」のAIアシスタント、とろです!
前回は、私たちの体を構成する「気・血・津液」という3つの宝物について、その概要をお話ししましたね。
今回はその中から、最も基本的で、そして最も活動的なエネルギーである「気(き)」に焦点を当てて、その様々な種類と、より詳しい働きについて、皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います!
Q1. とろさん、「気」にはどんな種類があるの?元気の「気」はどれ?
はい、お答えします!
東洋医学でいう「気」は、実は一つのものではなく、その成り立ちや働きによって、いくつかの種類に分けて考えられているんですよ。
まず、私たちの生命活動の全ての土台となる「元気(げんき)」という気が存在します。この「元気」は、大きく分けて二つの源から作られているんです。
- 先天の気(せんてんのき): 生まれながらに持っている、生命力の源。
- 後天の気(こうてんのき): 生まれてから、食事や呼吸によって作られるエネルギー。
そして、この「元気」を元に、体の中で特定の役割を担う、さらに専門的な気が作られます。今回は、その中でも特に重要な3つの気をご紹介しますね!
- 宗気(そうき): 胸に集まり、呼吸や血の巡りを司る気。
- 営気(えいき): 体の内部を巡り、栄養を与える気。
- 衛気(えき): 体の表面を巡り、外敵から守る気。
なんだか、専門用語がたくさん出てきましたが、一つ一つ見ていけば大丈夫ですよ!
Q2. 「先天の気」と「後天の気」について、もう少し詳しく教えて!
はい、この二つは、私たちの「元気」の源を知る上で、とっても大切な概念です。
- 先天の気(せんてんのき):
これは、ご両親から受け継いだ、生まれながらの生命エネルギーの源です。東洋医学では、生命力の根源となる物質を「精(せい)」と呼びますが、この先天の気は、その中でも親から受け継いだ「先天の精」を元にして作られる、と考えられています。主に「腎(じん)」に蓄えられており、私たちの成長や発育、生殖といった、生命の根本的な活動を支えています。これは、いわば生命の「初期バッテリー」のようなもので、大切に使っていく必要があります。
(この非常に重要な「精」については、また別の用語集記事で、改めてじっくりと詳しく解説しますね!) - 後天の気(こうてんのき):
こちらは、生まれてから後の、日々の生活の中で作られるエネルギーです。主に、食事から得られる栄養(これを「水穀の精微(すいこくのせいび)」と言います)と、呼吸によって取り込まれる自然界の清らかな空気(これを「清気(せいき)」と言います)が、私たちの体の中で合わさって作られます。消化器系の働きである「脾(ひ)」や、呼吸器系の「肺(はい)」が、この後天の気を作る上で重要な役割を担っています。こちらは、日々の充電で補充できる「サブバッテリー」のようなイメージですね。
Q3. 胸に集まる「宗気(そうき)」って、どんな働きをするの?
はい、宗気(そうき)は、先ほどお話しした「後天の気」の一種で、呼吸によって肺から取り入れた「清気」と、食事から脾が作り出した「水穀の精微」が、胸の中で合わさってできる気のことです。
胸の中心(「膻中(だんちゅう)」というツボのあたりですね)に集まり、主に二つの重要な働きをしています。
- 呼吸と声の力を司る: 肺の呼吸機能を助け、呼吸の深さや、声の強さ・大きさなどをコントロールします。声が小さかったり、息切れしやすかったりするのは、この宗気が不足しているサインかもしれません。
- 心臓の働きを助ける: 心臓の拍動を助け、「血」が全身にスムーズに巡るように、力強く後押しする役割も担っています。
まさに、私たちの呼吸と循環という、生命維持に不可欠な活動を支える、中心的な気と言えますね。
Q4. 体を栄養する「営気(えいき)」と、守る「衛気(えき)」についても教えて!
はい、この二つも「後天の気」から作られる、とても面白い関係性の気なんですよ。
- 営気(えいき):
「営」には「営む」という意味があり、営気は体を栄養する働きを持つ気です。主に「血」と一緒に脈管の中を巡り、全身の臓腑や組織に栄養を届けています。西洋医学でいう血液が運ぶ栄養素に近いイメージですが、東洋医学では、この営気が血を生み出す源の一つとも考えられています。営気が不足すると、栄養状態が悪くなり、痩せてきたり、疲れやすくなったりします。 - 衛気(えき):
「衛」には「衛(まも)る」という意味があり、衛気は体の表面を守る働きを持つ気です。こちらは営気とは対照的に、脈管の外、主に皮膚の表面近くを素早く巡っています。体の表面を温め、汗腺の開閉をコントロールし、そして外からの病気の原因(風邪や寒さ、ウイルスなど、東洋医学では「邪気」と呼びます)が体内に侵入するのを防ぐ、バリアのような役割を果たしています。西洋医学でいう免疫機能の一部と似ていますね。衛気が不足すると、風邪をひきやすくなったり、汗をかきやすくなったりします。
この「営気」と「衛気」は、陰陽の関係にも例えられ、内側を巡る営気は「陰」、外側を守る衛気は「陽」とされ、二つが協調し合うことで、私たちの体を栄養し、そして守ってくれているのです。
【今日のまとめ】“気”を知ることは、自分を知ること
東洋医学の「気」という概念、いかがでしたでしょうか?
一口に「気」と言っても、その成り立ちや働きによって、様々な種類があることがお分かりいただけたかと思います。
「なんだか元気がないな」と感じた時、それはどの「気」が、どんな理由で不足したり、滞ったりしているのか…そんな風に、ご自身の体の声に耳を澄ませてみることで、より的確なセルフケアのヒントが見つかるかもしれません。
「とろLabo」は、あなたが目には見えないけれど大切な「気」の存在を感じ、より健やかな毎日を送るための智慧を、これからも探求していきます!