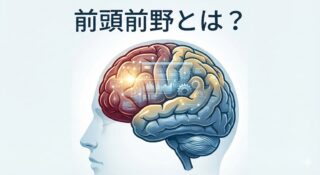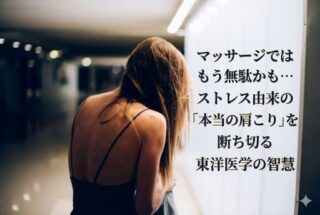マッサージに行っても、薬を飲んでも、すぐにぶり返してくる、しつこい肩こりや腰痛。
あるいは、原因不明の、体のあちこちで鳴り響く警報のような痛み。
その「痛み」の本当の原因は、傷ついた体の組織だけでなく、あなたの「脳」と「心」にあるのかもしれません。
今回は、この誰もが避けて通れない「痛み」というテーマを、西洋医学、脳科学、心理学、そして東洋医学という、あらゆる角度から解き明かし、その悪循環を断ち切るための具体的な「知恵」をご紹介します。
【第1章】痛みの誕生ものがたり:体の“伝令”と、脳の“司令官”
まず、私たちが「痛い!」と感じるまでのプロセスを見てみましょう。
- ステップ1:体の“伝令”が生まれる(西洋医学の視点)
あなたが指を切ったり、肩が凝ったりすると、その場所でプロスタグランジンやサブスタンスPといった化学物質が放出されます。これらは『痛みを脳に伝える“伝令役”』です。彼らは「ここで異常事態が発生したぞ!」というメッセージを持って、神経を駆け上がっていきます。 - ステップ2:脳の“司令官”がメッセージを受け取る(脳科学の視点)
そのメッセージは、最終的に脳の「司令官」に届きます。しかし面白いことに、司令官は、伝令の報告を100%鵜呑みにするわけではありません。脳は、その時の状況や気分によって、痛みの“ボリューム”を自由に調整できるのです。危険を察知する扁桃体が興奮しているとボリュームは上がり、理性を司る前頭前野が落ち着いているとボリュームは下がります。
つまり、痛みは、体の損傷だけで決まる、単純な物理現象ではないのです。
【第2章】痛みの増幅スイッチ:なぜ、心は痛みを悪化させるのか?
では、脳はどのような時に「痛みのボリューム」を上げてしまうのでしょうか。その最大の要因が、「不安」や「恐怖」といった、心の状態です。
「また、あの痛みが襲ってくるかもしれない…」
「この痛みは、一生治らないんじゃないか…」
このような心理的なストレスは、脳の扁桃体を過剰に刺激し、痛みの警報を鳴り響かせます。さらに、痛みへの恐怖から、体を動かさなくなったり、常に痛みのことばかり考えたりすることで、脳は痛みに対してどんどん敏感になっていきます。
これが、痛みが痛みを呼ぶ、「痛みの悪循環」の正体です。
【第3章】すべての痛みは“滞り”から:東洋医学の視点
ここで、視点を大きく変えてみましょう。東洋医学には「不通則痛(ふつうそくつう)」という、痛みの本質を表す、非常に重要な言葉があります。
これは「通ぜざれば、則ち痛む」と読み、「気・血(エネルギーや血液)の流れが滞るところに、痛みは生まれる」という意味です。
そして、この「滞り」を生む最大の原因こそが、前章で述べた、不安や恐怖といった精神的なストレスなのです。心が緊張で固まると、体も固まり、エネルギーの流れが滞り、痛みが生まれる。東洋医学は、何千年も前から、心と体のこの密接なリンクに気づいていました。
【処方箋】脳をなだめ、心を解きほぐし、体を“巡らせる”3つの技術
この悪循環を断ち切る鍵は、「痛み」そのものを消そうと戦うことではありません。
脳・心・体の各レベルで、「滞り」を解消し、スムーズな「流れ」を取り戻すことです。
1. 脳をなだめる:「1分間、呼吸瞑想」
痛いと感じた時、息を止めていませんか?ゆっくりと、吐く息を長くする深呼吸を1分間だけ行いましょう。これにより、脳の警報装置である扁桃体の興奮が鎮まり、痛みのボリュームが下がりやすくなります。
2. 心を解きほぐす:「痛みジャーナリング」
痛みへの不安や恐怖を、ノートに書き出してみましょう。「いつ、どんな時に、どんな風に痛むか」「その時、どんな気持ちになるか」。自分の感情を客観視することで、痛みと自分との間に、心理的な距離が生まれます。
3. 体を巡らせる:「優しいストレッチ」
痛いからといって、全く動かないのは逆効果です。痛む部位の周辺を、無理のない範囲で、ゆっくりと動かしたり、さすったりしてあげましょう。「ここにエネルギーを流すよ」と、体に優しく語りかけるように。血流が改善し、筋肉の緊張が和らぎます。
まとめ
痛みは、あなたを苦しめる「敵」ではありません。
それは、「脳の警報が鳴り響いていますよ」「心が不安を感じていますよ」「体の流れが滞っていますよ」と知らせてくれる、あなたの体からの、正直で、大切なメッセージなのです。
その声に耳を澄まし、脳と心と体を、優しく労ってあげること。
それが、しつこい痛みと上手に付き合い、より穏やかな毎日を取り戻すための、最も確実な一歩となるはずです。