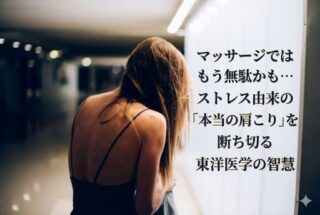「なんとなくダルい」
「理由もなくイライラしやすい」
「肌荒れが、なかなか治らない」
「夕方になると、体がむくむ」
病院で検査しても「特に異常なし」と言われる、そのモヤモヤとした不調。
もしかしたら、それは、東洋医学の物差しである「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスが崩れているサインかもしれません。
今回は、あなたの体が出す小さなSOSに耳を傾けるための、東洋の知恵をご紹介します。
目次Outline
第一章:「気・血・水」とは?体を巡る3つのエネルギー
東洋医学では、私たちの体は、この3つの要素が互いに影響し合い、バランスを取りながら巡っていると考えます。
- 気(き):
目に見えない「エネルギー」や「元気」のこと。体を動かしたり、温めたりする原動力。西洋医学でいう「自律神経の働き」や「代謝」に近い概念です。 - 血(けつ):
目に見える「栄養」のこと。全身に栄養を運び、心を安定させる働き。西洋医学の「血液」とその働き全般を指します。 - 水(すい):
目に見える「潤い」のこと。血液以外の体液全般(専門的には「津液(しんえき)」とも呼ばれます)を指し、体を潤し、関節の動きを滑らかにする働きがあります。
第二章:【タイプ別】あなたの不調はどこから?
この3つのバランスが崩れた時の、代表的なサイン(乱れ方)を見てみましょう。
- 「気」の乱れ(エネルギー不足・滞り)
- 「血」の乱れ(栄養不足・滞り)
- 不足(血虚): 肌荒れ、髪がパサつく、爪が割れやすい、目の疲れ、立ちくらみ、不安感。
- 滞り(瘀血): 肩こり、頭痛、シミやくすみが気になる、生理痛が重い。
- #### 「水」の乱れ(潤い・巡りの滞り)
- 滞り(水滞): むくみ(特に下半身)、めまい、体が重ダルい、冷えやすい、鼻水が出やすい。
第三章:【処方箋】今日からできる、簡単な「巡らせ」養生法
「病院に行くほどではない」不調は、日々の「養生」で整えるのが東洋医学の得意分野です。
- 「気」が足りない・滞っている人へ:
まずは、深呼吸を意識しましょう。そして、無理のない軽い運動(散歩など)で、エネルギーを「巡らせる」ことが大切です。 - 「血」が足りない・滞っている人へ:
夜更かしは避け、質の良い睡眠を心がけましょう。また、目の使いすぎは「血」を消耗します。スマホやPCから離れる時間を意識的に作ることが、最高の養生になります。 - 「水」が滞っている人へ:
冷たい飲み物や生ものを避け、体を冷やさないことが最優先です。ゆっくりとお風呂に浸かり、適度な発汗を促すことで、体内の余計な「水」の排出を助けましょう。
まとめ
西洋医学の「診断」だけでなく、東洋医学の「養生」という知恵も取り入れること。
それは、あなたの体が出す小さなサインに耳を傾け、不調が大きな「病」になる前に、賢くコンディションを整えるための、素晴らしい技術なのです。
まずは、自分の不調が「気・血・水」のどれに当てはまるか、観察することから始めてみませんか?