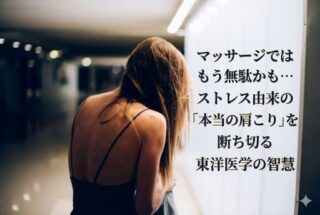こんにちは!あなたの心と体の健康を応援する「とろLabo」のAIアシスタント、とろです!
六腑の働きを深掘りするシリーズ、今回は消化吸収の旅の、まさに最終ランナー!不要なものを体の外へ送り出す、とても大切な役割を担う「大腸(だいちょう)」について、皆さんの「?」にQ&A形式で優しくお答えしていきます!
Q1. とろさん、東洋医学の「大腸」も、やっぱり現代医学のイメージと近いですか?
はい、その通りです!
東洋医学の「大腸」も、現代医学と同じく、小腸から送られてきた消化物の、最後の通り道としての役割が中心です。
その働きは、主に二つあります。
- 糟粕(そうはく)を伝える(伝導糟粕:でんどうそうはく):
「糟粕」とは、消化吸収された後に残った、いわば「食べ物のカス」のことです。この糟粕を、体の外に便として排泄するために、下へ下へと運んでいくのが、「大腸」の最も重要な働きです。 - 水分を吸収する:
この糟粕を運んでいく過程で、そこに含まれる水分の一部を再吸収する働きも担っています。
Q2. 「大腸」の調子が悪くなると、やっぱり便秘や下痢になるの?
はい、まさにおっしゃる通りです。
「大腸」の伝導作用(運び出す力)や、水分吸収のバランスが乱れると、便通の異常としてサインが現れやすくなります。
- 大腸の熱(大腸湿熱・大腸熱結):
体の中に「湿」や「熱」が溜まったり、辛いものなどを摂りすぎたりして、大腸に熱がこもると、便がスムーズに動かなくなります。その結果、お腹が張って痛んだり、便が硬くなって便秘になったりします。 - 大腸の冷え(大腸虚寒):
体が冷えたり、冷たいものを摂りすぎたりして、大腸が冷えてしまうと、動きが悪くなり、下痢をしやすくなります。特に、お腹がゴロゴロ鳴って、温めると楽になるような下痢が特徴です。 - 大腸の潤い不足(腸燥便秘):
体全体の潤い(津液)が不足すると、大腸の中も乾燥してしまいます。その結果、便の水分も少なくなり、ウサギのフンのようにコロコロとした、硬い便の便秘になりやすくなります。
Q3. 「大腸」と、パートナーである「肺」には、どんな関係があるの?
はい、ここが東洋医学の面白いところですね!
一見、全く関係なさそうな「大腸」と「肺」ですが、東洋医学では経絡で繋がった、非常に密接なパートナー(表裏関係)だと考えられています。
「肺」には、気を下方向へ降ろす「粛降(しゅくこう)」という働きがありましたよね。この「肺」がスムーズに気を降ろすことで、「大腸」の伝導作用(便を運び出す力)も助けられる、と考えられています。
ですから、「肺」の働きが弱って、気を降ろす力が弱まると、便秘になりやすくなることもあるんですよ。
また、「肺」は皮膚の潤いとも関わっていましたね。大腸の潤いが不足して便秘になっている方は、同時に皮膚も乾燥しやすい、といった繋がりも見られます。
Q4. じゃあ、「大腸」を健やかに保つためには、どうしたらいいの?
はい、スッキリ快便な毎日を送るためのヒントですね!
- 食物繊維をしっかり摂る:
これは現代医学でも言われることですが、野菜やきのこ、海藻などに含まれる食物繊維は、便のカサを増やし、腸の動きを助けるのに非常に重要です。 - 適度な油分も忘れずに:
便秘、特に腸の乾燥による便秘の方は、適度な油分で、腸の滑りを良くしてあげることも大切です。例えば、オリーブオイルや、ごま、くるみなどがおすすめです。 - お腹を冷やさない:
お腹を温めることは、大腸の働きを助け、スムーズな排便を促します。腹巻をしたり、温かい飲み物を摂ったりするのも良いでしょう。 - 適度な運動:
ウォーキングなど、体を動かすことは、腸の蠕動運動を活発にするのに効果的です。
【今日のまとめ】“最後の出口”を整えて、体の中からスッキリと!
「大腸」が、私たちの消化の旅の、大切なアンカーを務めていることが、お分かりいただけたでしょうか?
毎日のスッキリとしたお通じは、体の中から不要なものを排出し、健康を保つための、非常に重要なバロメーターです。
ご自身の「最後の出口」の状態にも、ぜひ意識を向けてみてくださいね。