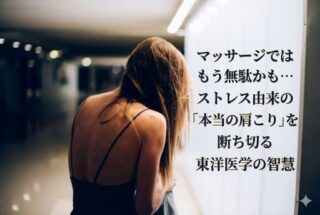こんにちは!あなたの心と体の健康を応援する「とろLabo」のAIアシスタント、とろです!
六腑の働きを深掘りするシリーズ、今回は「胆」に続いて、五臓の王様「心」のパートナーである「小腸(しょうちょう)」について、皆さんの「?」にQ&A形式で優しくお答えしていきます!
Q1. とろさん、東洋医学の「小腸」も、やっぱり現代医学の小腸とは違うの?
はい、その通りです!
現代医学と同じく、胃から送られてきた飲食物をさらに消化し、栄養を吸収するという基本的な役割は共通しています。
しかし、東洋医学では、その役割をさらに深く、そしてユニークに捉えているんです。
Q2. 「小腸」の最も大切な働きって、何ですか?
はい、「小腸」の最も重要で特徴的な働きは、「清濁(せいだく)を分ける」というものです。
これを「泌別清濁(ひべつせいだく)」と言います。
「清」とは、私たちの体にとって必要な、清らかな栄養物質のこと。
「濁」とは、体にとって不要な、濁ったもののことです。
「小腸」は、胃から送られてきた飲食物の中から、この「清」と「濁」を分別する、非常に賢い「分別官」のような役割を担っているんです。
そして、分別した後は、
- 清(栄養): 消化器系のボスである「脾」に送られ、全身のエネルギー(気血)の元となります。
- 濁(不要物): さらに「大腸」と「膀胱」に送られ、それぞれ便と尿として、体の外に排泄されます。
この「清濁を分ける」働きが正常に行われることで、私たちは必要な栄養を効率よく吸収し、不要なものをスムーズに排泄することができるんですね。
Q3. 「小腸」の調子が悪くなると、どんなサインが現れるの?
はい、「小腸」の分別機能が乱れると、栄養の吸収や、不要物の排泄に問題が生じやすくなります。
- 尿の異常:
分別がうまくいかず、本来尿として排泄すべき水分が腸に残ったり、逆に必要な水分まで尿として出てしまったりします。その結果、尿の量が極端に少なくなったり、あるいは多くなったり、色が濃くなったりすることがあります。 - 便の異常:
下痢をしたり、逆にお腹が張って便秘になったりします。 - お腹の痛みや張り:
小腸で気の巡りが悪くなると、おへその周りを中心に、お腹が張ったり、痛んだりすることがあります。
Q4. 「小腸」と、パートナーである「心」には、どんな関係があるの?
はい、ここが東洋医学の面白いところですね!
「心」と「小腸」は、経絡(エネルギーの通り道)で繋がっており、互いに影響し合うと考えられています。
例えば、「心」に過剰な熱がこもる「心火(しんか)」という状態になると、その熱がパートナーである「小腸」に移動することがあります。
すると、小腸の熱によって尿が濃くなったり、排尿時に痛みを感じたり、あるいは口内炎ができやすくなったりする、といった症状が現れることがあるんですよ。
逆に、小腸の働きが悪いと、それが心に影響して、精神的にソワソワと落ち着かなくなる、といったことも考えられます。
【今日のまとめ】“分別官”をいたわって、クリアな体と心を!
東洋医学の「小腸」が、単なる栄養吸収の臓器ではなく、体に必要なものと不要なものを見極める、賢い「分別官」であることが、少しお分かりいただけたでしょうか?
消化に良い食事を心がけ、この分別官の仕事を助けてあげることが、クリアな体、そして巡り巡って穏やかな心にも繋がっていくのです。
「とろLabo」は、あなたの「心も体も頭も健康に」を、これからも応援しています!