
この記事では、お酒の適量とアルコールが分解されるプロセスについてお伝えします。
アルコールの適量は20g
「通常のアルコール代謝能を有する日本人においては、節度ある適度な飲酒として、1日平均純アルコールで==20g==程度である。」
「e-ヘルスネット/アルコールの吸収と分解」より
お酒に含まれるアルコールの量を求める式は次のとおりです。
アルコールの量(g) = お酒の量(ml)× 度数 ÷ 100 × 0.8
例えば、アルコール度数5%の350mlのビールの場合、
アルコールの量(g) = 350ml × 5% ÷ 100 × 0.8
となり、
「14g」
がアルコールの量になります。
具体的にどれくらい?
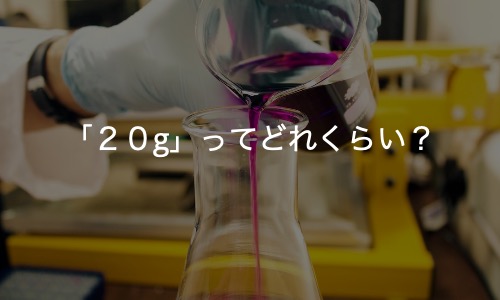
「20gのアルコール」というのは、具体的にどのくらいの量なのでしょうか?
大まかな目安が次の通りです。
| お酒 | 量 |
|---|---|
| ビール中ビン | 1本 |
| 日本酒 | 1合 |
| 焼酎水割り | 1杯 |
| チューハイ(7%)350ml | 1本 |
| ウイスキー(ダブル) | 1杯 |
| ワイン(グラス) | 1杯 |
お酒の適量(ml) = 2500 ÷ 度数(%)
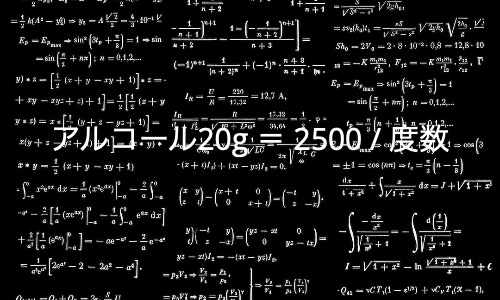
お酒の適量は、「2500➗度数」で求めることができます。
例えば、アルコール度数が5%のビールの場合、
2500 ÷ 5 = 500ml
ということになり、
「500ml」が適量となります。
お酒のカロリーはエンプティーカロリー?
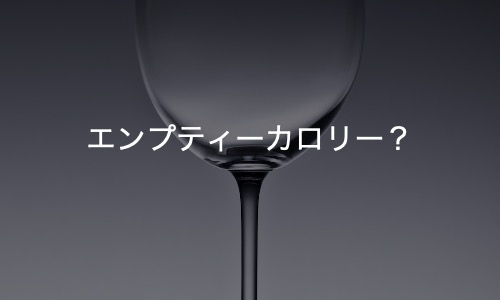
アルコール1gに含まれるエネルギーは7.1キロカロリーです。
1日あたりのアルコールの適量20gで計算すると、142キロカロリーとなります。
ところで、アルコールのエネルギーは体内に蓄積されにくいことから「エンプティーカロリー」と呼ばれます。
「蓄積されない」とか「エンプティー(=空っぽ、空虚)」と聞くと、とても魅力的ですね。
「お酒はいくら飲んでも太りません。」
と、言いたいところですが、そんなことはありません。
その理由は次の2点です。
- お酒のカロリーが優先的に消費される。
→ そのほかの食べ物のカロリー消費は後回し
→ 蓄積される。
→ つまり、脂肪になります。 - アルコールを分解する過程で中性脂肪が作られる。
→ つまり、脂肪になります。
こうしたことから、太りやすい状態になってしまうわけです。
「エンプティーカロリー」食品は、だいたい、肥満や生活習慣病につながるので気をつけないといけません。
ファーストフードなんかもこれにあたるので、食べるときには、そのことも理解した上で、計画的に食べていきましょう。
アルコール分解にかかる時間は?

1時間で分解できるアルコールの量には、個人差があるようですが、概ね次のとおりです。
| 男性 | 9g |
| 女性 | 6.5g |
アルコールを20g摂取した場合、
- 男性 2時間13分くらい
- 女性 3時間ちょっと
です。
これはあくまでも目安で、年齢や体格、体質等によって異なります。
お酒にいくら強くても、分解するのには時間がかかるので、お酒を飲んだら車の運転はしないようにしましょう。
アルコールに強い人と弱い人の違いはなに?
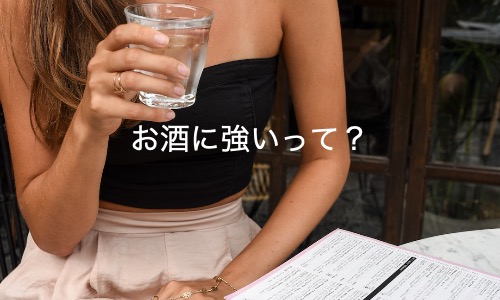
「お酒に強い」とか「お酒に弱い」とかいうことがありますが、これは、アルコール分解能力によって決まります。
アルコールの分解には2つの酵素が関係しています。
その酵素が、
- アルコール脱水素酵素(アルコールデヒドロゲナーゼ)
- アルデヒド脱水素酵素(アルデヒドデヒドロゲナーゼ)
です。
特に、アルデヒド脱水素酵素のタイプによって「お酒の強さ」が変わってきます。
アルコールが分解されるまで

アルコールは消化管で吸収されて肝臓に運ばれる
飲む → 消化管 → 上腸間膜静脈、下腸間膜静脈 → 門脈 → 肝臓 アルコールは、消化管で吸収されます。
その後、静脈(上腸間膜静脈や下腸間膜静脈)に流入していきます。
その静脈が合流して、門脈と呼ばれる静脈に流入し、門脈を経て肝臓に運ばれます。
肝臓の酵素によって分解される
肝臓では、2つの酵素によってアルコールの分解が行われます。
- アルコール脱水素酵素
アルコール ⇨ アルデヒド - アルデヒド脱水素酵素
アルデヒド ⇨ 酢酸
最後は筋肉や各種臓器で分解される
酢酸は、筋肉や各種臓器で分解される。
肝臓 → 肝静脈 → 下大静脈 → 心臓 → 筋肉や各種臓器
お酒に強い人と弱い人の違いは?

お酒が強い人と弱い人を分けているのが、アルデヒド脱水素酵素のタイプです。
アルデヒドは、頭痛や吐き気、紅潮などのフラッシング反応を引き起こす物質で、二日酔いの原因物質でもあります。
このアルデヒドを分解し、無力化してくれるのがアルデヒド脱水素酵素です。
アルデヒド脱水素酵素には、活性型と低活性型、非活性型の3つのタイプがあります。
- 活性型
アルデヒドを速やかに分解してくれるタイプ。そのため、血中のアルデヒド濃度が上昇しにくい。 - 低活性型
アルデヒドの分解に時間がかかってしまうタイプ。そのため分解されるまでの間、血中のアルデヒド濃度が上昇する。 - 非活性型
アルデヒドを分解できないタイプ。血中アルデヒド濃度が高い状態が続いてしまう。
お酒が強いといわれる人は、遺伝的に「活性型」のアルデヒド脱水素酵素を持っています。
そのため、アルデヒドが速やかに分解され、頭痛などが起こりにくいということになります。
このタイプの酵素を持っている人は、結構な量のお酒を飲んでも、頭が痛くなったり、吐いたりしないわけです。
逆に、低活性型、非活性型の場合は、そういうわけにはいかず、お酒を飲む音ですぐに顔が赤くなったり、頭痛、吐き気に襲われることになります。
なので、お酒に強いとか、弱いとかというのは根性とかそういうのではないんですね。
まとめ

- アルコールの適量は20g
- アルコール20gのお酒の量 = 2500 ÷ 度数
- アルコール1gあたり7.1キロカロリー
- エンプティーカロリーは蓄積されないけど、太りやすくなる。
- お酒を飲んだら車の運転はしない。
私がこの記事を書いたよ!
テリー
いつも自由にやらせてもらってますが、最近、健康のことにも気を使わないとなと思い、ブログを書きながら、自分自身も健康に対する意識を高めてみようかなと考えています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持っているので、体のことや健康のことにはそれなりに詳しいです。 なぞなぞと手品が大好きです。


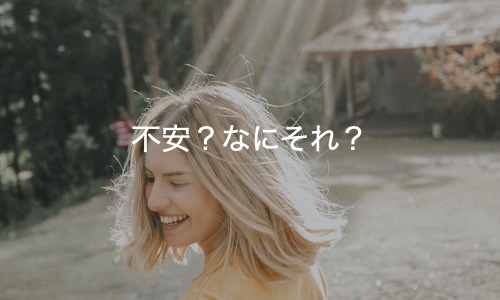
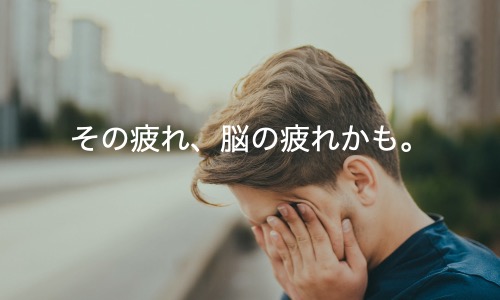
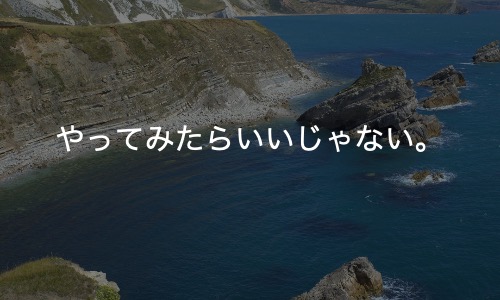



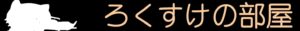
コメントを書く